大事な我が子が、はじめて社会生活を送る場となる「園」選び。とっても悩みますよね。
私も息子たちの入園前には、「どの園がいいかな?」と悩み、たくさん調べました。
そこで今回は、我が子の「園選び」で悩んでいるママやパパに向けて、
保育園・幼稚園・こども園の違いにも触れながら、園選びの参考となるような記事を書いていきたいと思います。
元保育園栄養士として保育現場を間近で見ていたことがあり、
息子2人(4歳、8歳)を、認定こども園に通園させている(兄に関しては卒園済み)ママの私が、
その経験をもとに、お伝えします!

保育園・幼稚園・こども園の違いについても記事内でまとめますが、そこは一般的なことを体系的にまとめただけなので、知っている方はそこは読み飛ばしてもらって。。
ぜひその下の「感想」「経験談」にあたる箇所をご参考頂ければと思います♪
保育園・幼稚園・認定こども園の違いとは?

小学校入学前の「未就学児」が通園できるところは、そもそも大きく分けて、「保育園・幼稚園・認定こども園」があります。
簡単な違いを表にまとめると以下のようになります。
| 園の種類 | 対象年齢 | 保育時間 | 給食 | 管轄 |
|---|---|---|---|---|
| 保育園 | 0〜5歳 | 長い(8〜11時間) | 原則あり | 厚生労働省 |
| 幼稚園 | 満3歳〜 | 短い(4〜5時間) | 施設による | 文部科学省 |
| 認定こども園 | 0〜5歳 | 両方あり | 原則あり | 内閣府 |
また、主な目的と特徴をまとめると、
保育園:
- 主な目的: 保育を必要とする就学前の子どもの保育
- 特徴: 保育士資格を持つ職員が、子どもの生活習慣や情緒の発達を促す
幼稚園:
- 主な目的: 就学前の子どもに教育を施す
- 特徴: 幼稚園教諭免許を持つ職員が、小学校就学に向けた教育を行う
認定こども園:
- 主な目的: 保育と教育の両方の機能を提供し、地域の子育て支援も行う
- 特徴: 幼稚園と保育園の両方の機能を併せ持ち、保護者の状況に合わせて利用できる
補足:認定こども園は2006年に制度としてスタートしましたが、2015年からの「子ども・子育て支援新制度」で、全国的に統一された仕組みへと整備されました。
感想|保育園とこども園(幼稚園)、ここが違う!

制度面では、保育園と幼稚園は近づいている
「保育園・幼稚園・認定こども園」は上の章でまとめたような違いがもちろんありますが、
2015年の「子ども・子育て支援新制度」以降、保育園(保育所)と幼稚園での教育・保育の内容やねらいを近づける努力がされています。
そしてどちらの園であっても小学校入学前の準備としての役割を意識しています。
なので、「保育園=保育を担う場、幼稚園=小学校前の教育を担う場」というわけでは、制度面ではなくなってきているということです。
実際に子どもが通園して感じた違い
制度面での違いは無くなってきているとはいえ、私自身が勤務先の保育園でみてきた環境と、息子たちが通園するこども園(幼稚園)では、雰囲気や中身がだいぶ違うなとも感じます。
私が特に感じる違いをいくつか挙げていきます。

息子たちの「こども園」は、0歳クラス~2歳クラスまでの園舎と、3歳~5歳クラスまでの園舎が、隣接していますが異なります。
3歳~通園する園舎は、「幼稚園舎」となり、幼稚園に通園する子(1号認定を受けている家庭)と、こども園に通園する子(2号認定を受けている家庭)が同じクラスで一緒に過ごす形式をとっています。
なので以下に挙げる違いは、3歳からの「幼稚園(こども園)」と「保育園」の違いという観点で書いていきますね!
■活動面
「幼稚園」「保育園」の違いではなく、「その園がどんな園か」によるのだと思いますが、息子たちの通園先からは、「プレ小学校感」を強く感じます。
決して教育重視な園ではなく、のびのびとした雰囲気を大事にしている園ですが、
- 玄関で上履きに履き替え、教室に自分で向かう
- お道具箱やピアニカを各家庭ごとに購入して、自分のものとして取り扱う
- 毎月、チャイルドブックが1人1冊ずつ配られて、それに沿った活動もある
こういったことは、私の勤務先(保育園)では見たことがない光景だったので、いわゆる幼稚園ならではの「教育面の強さ」を感じました。

活動の一部として、体操や音楽(リトミック)、英語の時間などがあるかどうかというのは、幼稚園と保育園で違うといったことは無く、その園ごとに決めていることかと思います。
通園先(幼稚園)、かつての勤務先(保育園)、どちらも全て行っていました。
■給食
給食に関して、幼稚園は仕出し弁当の給食を提供しているところが多く、
保育園は自園調理(敷地内でつくった給食)を提供しているところが多い印象を受けます。
給食を作るという仕事を選択している身としては、やはり、仕出し弁当より、自園調理の給食の方が、こまやかで美味しいと思っています。

2号認定(保育が必要)を受けて、幼稚園(こども園)に通園している息子たちはというと、毎日、隣の保育園施設で作ってもらった弁当(給食)を食べています。
同じ園に通園している子でも1号認定(教育のみ必要)の子たちは、仕出し弁当給食を週3日、持参した弁当を週2食べています。
こういった混在したか形になるのが、「こども園」ならではだと思います。
■保育時間
保育してもらえる時間は、当然ながら保育園、こども園が長くなりますが、
最近では幼稚園も預かり保育が充実しているので、それを利用すれば大きな差はないかなと思います。
ただし、年末年始の数日以外は、お盆でも年度末でもずっと開園している保育園、こども園に対して、
幼稚園では、預かり保育も休園となるお盆休みや春休みがあったりするので、共働き家庭では注意が必要かなと思います。
経験談|「園選び」で大切にしたこと、よかったこと

今現在、長男は卒園し、次男は年中さんとして通園していますが、私自身は親として、「この園を選んでよかった」と思っています。
なので、私自身が入園前の決め手としたことと、入園後によかったと感じたことを挙げていきます。
入園前の決め手となったこと
■園長先生や主任の雰囲気が良い
保育園、幼稚園に関わらず、組織すべてにおいて言えることだと思いますが、
やはりTOPがよい園は、園の雰囲気がいいです。
子どもたちの1番身近な存在となる、担任の先生の雰囲気が良いことも大切ですが、入園前にどの先生に担当して頂けるかも分かりません。
先生方を束ねる、上の立場となる、主任の先生や園長先生はそう変わることもないので、その方々がしっかりしているか、家庭の考え方と合った先生であるかを見ることは大切だと思います。
園見学の際に言葉を交わすチャンスがあると思うので、我が子を「任せられる先生か、任せたい先生か」意識して見てみてください。

系列園をたくさんもつような園では、TOPである園長先生や主任の異動が頻繁に行われる場合もあるので注意が必要です。
(そういった園がダメというわけではありません。ただ系列園が多い園だと、先生で選んでも、異動が多いこともあるというのを心にとめておきましょう。)
■安全への意識が高い
園生活においてなによりも大事なことは、安全安心であることだと思います。
まだ小さな子どもたちは、自分で自分の身を守ることが出来ません。
こどもたちの通園中の悲しい事故のニュースも毎年必ず目にします。
園の設備、給食、先生方の意識や対策が、安全面でしっかりと確保されている園を選ぶことは、なにより大切だと思います。
入園後によかったなと思ったこと
■時代に沿った変化への意識がある
世の中はどんどん変化し、今やAIやロボットの活躍が、日常生活の一部となりつつあります。
子どもたちが大人になるころは、そういった人間ではないモノが、きっとライバルとなりうるし、仲間となりうる世界だと思っています。
通園先では、そういった世の中で生き抜いていく力を育てていきたいという意識をもって保育教育をしてくれています。
(いわゆる、非認知能力を大切にしようとしてくれています。また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」も大切にしてくれています。)
■非認知能力とは?
*テストでは測れない「生きる力」
思いやり・がんばる力・自分で考える力など、園活の中で自然に育つ「目に見えにくい大切な力」のこと
■幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿とは?
*小学校に入るまでに育ってほしい力を10個にまとめたもの
保育園・幼稚園・こども園すべてに共通していて、子どもの“育ちの方向”を大人が一緒に意識できるようにした目安
どれくらい、保育や教育の現場で実践できるのかは難しいところだと思いますが、
どんどん変わりゆく時代や、教育観に対して前向きに学ぶ姿勢を持っていてくれることは、親としても嬉しいことだし、子どもたちにとってもプラスだと思っています。
■職員の異動が少ない
保育業界って、資格職なこともあるためか、すごく流動的なのですが。。(転職がとっても多い)
通園先は、辞めていく先生がとても少ないことに驚き、そして安心しました。
やはり、先生が変わらないというのは、組織として安定感もあるし、先に書かせてもらった、安全面も守られやすくなると思います。
そして辞めることが少ないというのは、ネガティブな感情が少ない中で、子どもたちを見てもらえることにつながっているかなと。(つながっているといいな。)
イライラ、イヤイヤした感情で子どもと接されるよりは、仕事を楽しんでいる先生に見てもらいたいのが親心です。
先生たちが辞めずに楽しく働ける環境が、通園先はもちろん、世の中として整備されていくといいなと思っています。
まとめ|大きな枠組みでなく、「どの園か」が大切

実は、私自身が7年前に長男の園選びをする際は、
幼児教育も意識したいとの思いもあり、「こども園」を中心に保活をしました。
けれどあれから時が経ち、ママ友たちと話している中で感じるのは、
「幼稚園」「保育園」「こども園」、体系的な違いはあるけれど、その大枠ごとに良い悪いがあるのではなく、個々のどの園を選ぶかで全然違うし、それこそが大切だということです。
私の自治体では、ここ数年で保育園がたくさん出来、幼稚園がこども園となる園も増えました。
(そしてその逆の、保育園がこども園になるといった園もあります。)
以前のような「とにかくどこか入れる園を見つける」ではなく、
各家庭が「園を選ぶ」時代に入ってきているのを感じます。
(実際に、保育の現場ではこれからは選ばれる時代だ!と危機感を持っている様子が見受けられます。)
色々と書きましたが、結局は各家庭にあった園が1番です。
繰り返しになりますが、この記事で1番伝えたいのは、
「保育園」「幼稚園」「こども園」といった大きな枠組みの違いもあるけれど、
それぞれ園ごとに全くカラーが違う!!
ということです。
保育園=保育中心、幼稚園=教育中心では決してないですし、
保育の中身もそれぞれ(アットホームか、社会性を大切にするのかetc)、
教育の中身もそれぞれ(読み書きを大事にしたい、話し合い活動を大事にしたいetc)です。
ご家庭でよく話し合って、ぜひ気になる園には足を運んで、
そして色々な意見も参考にしながら、園選びを楽しんでいってくださいね♪
この記事が、どなたかの園選びの参考に少しでもなれたら幸いです。

園選びに絶対はありません。もし後悔したら、転園することもできます。
ただ転園は、心身ともに、そして金銭的にも負担もあると思います。
我が子のためにも、なんとなく決めるではなく、よく考えて選択することは大切かなと思います!
~おしまい~
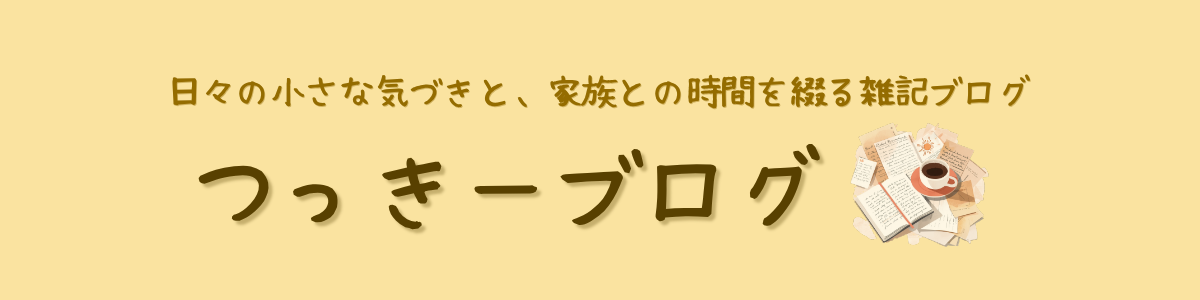
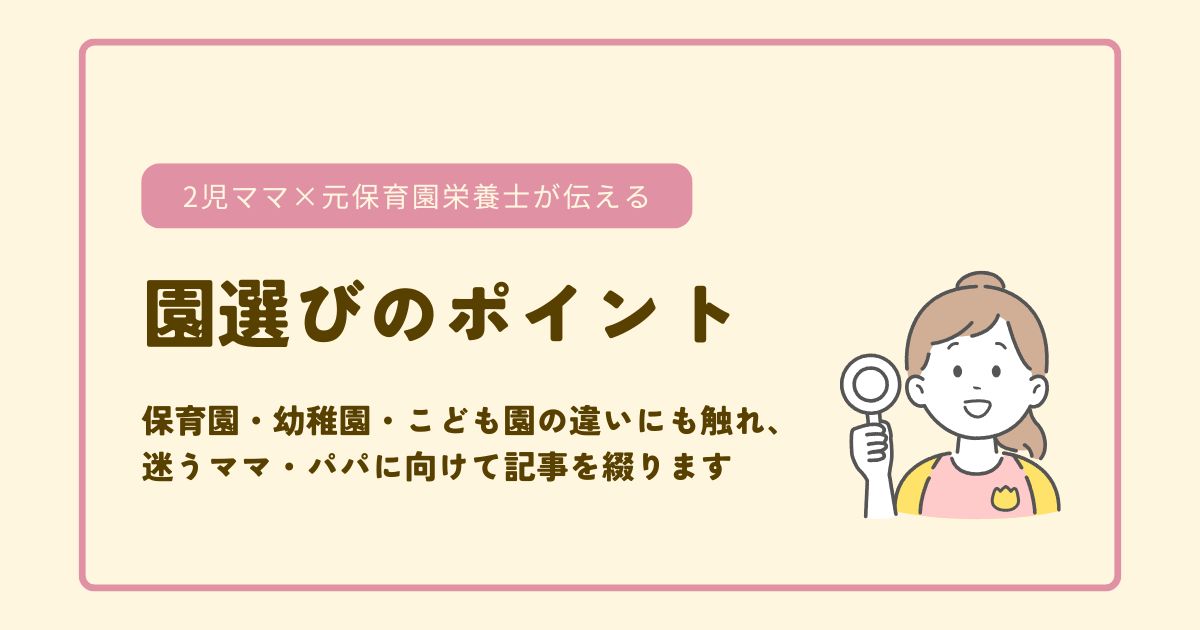

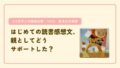
コメント